こちら(↓)の記事をまだ読んでない人は必ず見てから、今回の記事をご覧ください。

時間が無くなったり、やる気が出なかったり…。
このせいでいつも計画倒れ。

計画って具体的に立てた方がいいのかな…?

いつもスマホを見ちゃって、計画がムダになります…。
今回は、こういった方のために挫折しない計画の立て方を具体的に紹介します!
ここでは、勉強計画を見直すポイント6つをそれぞれ徹底解説していきます。
この記事を読めば、「今日も勉強できる!」という自信を毎日持てるようになります!
- 計画は逆算して立てる【超基本!】
- 目の前のことは具体的に ⇔ 中長期的な目標はざっくりと
- 挫折や誘惑から立ち戻った回数をカウントする
- ”頑張ればできる”だけの目標になっていないか?
- ”バックアッププラン”を立てられているか?
- 「~しない!」という目標になっていないか?
【超基本】計画は逆算して立てる

計画はゴールから逆算して立てましょう。
しかし、よく

とりあえず、持ってる参考書を片っ端からやってやるー!!
などと、やみくもに勉強し続ける人がいます。
例えば、
・”とりあえず”チャート1日3問解くか。
・”なんとなく”昨日の復習すればいいかな。
という人です。
こういうことを無意識にやってしまう人は結構多いです。
しかしそれでは「計画を立てた」とは言えません!
そこでポイントとなるのが「逆算思考」です。
「逆算」という言葉を聞いて、
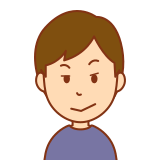
はいはい。そんなのよく聞くから分かりきってるし。
と思っている人、本当に「逆算」できているでしょうか。
正しく理解するために、次の例を見てください。
最終的な目標:「京都大学に合格すること」
←「そのためには、入試直前に何をやればいいだろうか?」
……過去問演習をする
←「では、過去問演習を効果的に行えるようにするためにはどうしたらいいのか?」
……苦手な分野が京大では頻出だから、克服しなければいけない
←「苦手分野を克服するためにはどうすればいいだろうか?」
……手持ちの分野別問題集で対策する
←「その問題集はどれだけ取り組めば十分か?」
……模試でその分野を80%~90%得点できるくらい
……次の模試まで1か月あるから1週間で7~13題解こう
「志望校合格」から逆算した場合はこのようになりましたが、「次回の模試」といった目標から逆算してももちろんOKです。
その場合は、もう少し具体的に逆算することになりそうです。
例えばこんな感じでしょうか。
最終的な目標:「次の共通テスト模試で得点率75~85%!」
←「各教科何点取れればいいだろう?」
……現代文=○点/古文=○点/~~~~~~
←「あ、特にリスニングの点数が欲しい。リスニングのどの分野が苦手だろうか?」
……第1問など、短い文を聞き取るのが苦手だな。でも、対話は比較的点数が取れる。
←「短文と対話文の点数に違いが出るのはなぜだろうか?」
……短文は、すばやく状況を把握しなきゃいけないから、正確に英語を聞き取らなければいけない。一方、対話文は文脈や構造から推定できる部分もあるから、自分はそれが得意なだけかもしれない。
←「推測して内容把握するのではなく、英文をしっかり聞き取る練習が必要だ」
←「単発の英文を聞きまくれる問題集をやろう」
……模試まであと30日。語学は習慣化が大事だから、毎日英語を聞き続けよう。
……通学時間はリスニング。電車の中では声を出せないから、頭の中でシャドーイング。
ここであげた逆算思考の例は、あくまで一例なので、皆さん一人一人の課題に向き合って「逆算思考」を行ってみてください。

逆算しなきゃいけないのはわかったけど、自分でやるとちょっと難しい…。
という人もいるかもしれません。
うまく逆算するためのコツ。それは
自分の目標に対して「疑問/質問」を投げかける
ということです。
具体例を見てもわかるように、
「○○ためにはどうすればいいだろうか?」
などと疑問を投げかけていますよね。
とはいえ慣れないうちは、うまく逆算できないことがあると思います。
そういうときは周りの人から情報を得ましょう。
・勉強できる子にアドバイスをもらう
・ネットで情報収集
などです。
× 「現時点 → 目標」 の流れでなんとなく計画を立てる
〇目標から逆算して計画を立てる
→コツ:ひたすら自問自答を繰り返してみよう。
目の前の行動計画は具体的に ⇔ 中長期的な目標は幅を持たせる
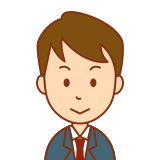
目標は具体的かつ明確に設定しましょう。
こんなこと、よく聞きますが…。
これは、半分正しくて半分間違っています。
具体的にすべきかどうかは、場合によって使い分けるべきです。
どういうことか。
すぐやらねばならないこと(1日の計画)は、具体的な目標にする。
一方、中長期的な目標(週間・月間目標)は、ざっくりとした目標にする。
「1日の計画を立てるときには具体的にしたほうが、手を付けやすくなる。」
それは皆さん納得してもらえると思います。
しかし、

じゃあ、手を付けやすくなるんだったら、
週間目標も具体的にやればいいんじゃないの?
と、思う人がいるかもしれません。
そこで、「1.逆算して計画を立てる」の例を見てみましょう。
「1週間で10題解くぞ!」ではなく
「1週間で7~13題解く」となっています。
さらに
「得点率80%!」ではなく
「得点率75%~85%!」となっていますよね。
なぜこういう幅を持たせたほうがいいのでしょうか?。
たとえば、

次のマーク模試で80%とるために頑張る!
と意気込んでいたのに、実際取れたのは75%だったとします。
そうすると、

あんなに勉強したのに…。
と言って自己嫌悪に陥ったり、勉強を投げ出したりしてしまう人だっています。
とくに直前期は深刻ですね。
そうではなく「75%~85%」と幅を持たせましょう。
しかし誤解しないでもらいたいのは、
目指すのは「80%」であることに変わりはない、ということです。
このようにざっくりとした目標を設定することで、
万が一80%を下回っても「75%は下回っていないから良し!」と前向きになれるし、
82%となって達成できたとしても「自分はまだいける!85%をめざそう!」と成長志向で考えることができます。
目の前の勉強計画 (ex.1日の勉強計画など)
→ なるべく具体的な目標
中長期的な勉強計画 (ex.1週間先,1か月先…)
→ ある程度幅のある目標
挫折や誘惑から立ち戻った回数をカウントする


ついつい勉強中にスマホを触ってしまった…。
こういう経験、皆さんも1回はあると思います。
Youtubeで時間を浪費して計画倒れした経験は、僕にもあります。
そんなときは、「スマホの誘惑を振り切った回数」をカウントしてみてください。
そうすれば、「回数を稼ごう!」と考えてモチベーションが上がります。
さらに、積み重ねてきた回数を意識することで「自分はできる」という感覚を持つこともできます。
例えば、こんな感じです。
【状況】
朝に投稿したTweetの反応が気になり、勉強中にスマホを見てしまう。
そしてそのまま、他の人の投稿も見続けてしまった。
【そこで、カウント法を実践する!】
あらかじめ「誘惑を振り切る」ことの定義を決めておく。
例えば「勉強中にもかかわらずスマホを見ている自分に気づいてから、5秒以内で勉強に戻る」ことができたら、1回カウントする、といったかんじです。
コレ、効果高めなのでやってみる価値はありますよ。
どうしてもスマホは見たくなる。
でも、そこから勉強を再スタートできるかが大事。
転んで立ち上がることができた数をカウントしよう。
”頑張ればできる”だけの目標はNG⁉

オイラは、高い目標のほうが自分を成長させることができるぞ!
という人もいますが、多くの人にはあてはまりません。
むしろ、

また目標達成できず…。
こんな自分が情けないよ…。
勉強のモチベが…。
ということのほうが多いです。
中には、
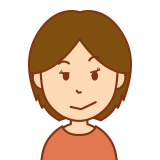
今日達成できなかった分は、明日に持ち越して頑張ればいいでしょ。
と考える人も多いです。
こう考えてしまうと、先延ばしっぱなしで結局達成できません。
なので、目標を立てたけど達成できなかったのなら、同じような目標を立てるのはやめましょう。
未達成の目標は、
「達成しやすいレベルに下げる」
「具体化してわかりやすい目標に修正する」
「別の方法を模索する」
などして手を加えるべきでしょう。
例えば、
「マーク模試75%はとる!」
という目標が達成できなかったとします。
その場合は、次のように修正すればOKです。
・実際の得点率が65%で、目標とは程遠い
⇒目標が高すぎるので、まず70%を目指す
・全教科合わせた目標だったので、具体的な対策が見えていなかった
⇒各教科ごとの目標点を決める
・そもそも基礎ができていないので、模試レベルで考えるのが間違っていた…
⇒学校の定期テストを目標にする
⇒問題集の正答率を目標にする
この例でも、
「達成しやすいレベルに下げる」
「具体化してわかりやすい目標に修正する」
「別の方法を模索する」
という3つの修正方法にしたがっています。
目標は、達成するためにある。
”頑張ればできる”は通用しない。
達成できる目標に修正しよう。
② 融通の利かない計画はNG
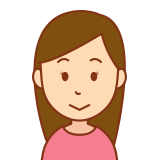
学校帰り、友人と1時間も話しちゃった…!

今日は疲れたから、あまり勉強できないなぁ。
こういうことってありますよね。
そういうときは、だいたい計画倒れしてしまいます。
しかし、このような事態はどうしても避けられません。
そういう場合に備えて、
「調子がいいとき用」の計画
「調子が悪い・時間がないとき用」の計画
この2つを用意しておきましょう。
たとえば、
「今日は順調だから、問題集ガッツリやろう」
「今日は帰りが遅くなっちゃったから、単語帳だけやろう」
というふうに使い分けるのです。
このように、いざという時のための計画を用意しておくと、
臨機応変に対応できる素晴らしい計画に様変わりします。
「時間がないとき用」
「疲れてしまったとき用」
「集中できないとき用」
など、いざという時のためのプランを考えておこう。
③ 「~しない!」という目標はNG
「スマホを触らない!」
「帰り際には、友人とは話さない!」
という目標は結構ツラいです。
そういう目標設定をするとかえって「スマホ」などに意識が向いてしまうからです。
例えば、

非常時以外は押さないでください。
とかいうボタンを見かけますが、そう言われるとなぜか押したくなってしまいますよね。(笑)
このように、人間は否定・禁止されると逆にやりたくなってしまう人間なのです。
なので、「○○ない!」ではなく
・「スマホを触るかわりに、本を読もう」
・「友人と雑談するかわりに、先生に質問しに行こう」
といった感じに、代替案を立てておくのがおすすめです。
ダメな目標:「○○しない」
→ 良い目標「○○する代わりに△△する」
まとめ & いざ実践!
- 計画は逆算して立てる【超基本!】
- 目の前のことは具体的に ⇔ 中長期的な目標はざっくりと
- 挫折や誘惑から立ち戻った回数をカウントする
- ”頑張ればできる”だけの目標になっていないか?
- ”バックアッププラン”を立てられているか?
- 「~しない!」という目標になっていないか?
計画の立て方のコツが理解できたら、いよいよ実践です。
こちらの記事でテンプレをダウンロードして使ってみてください。

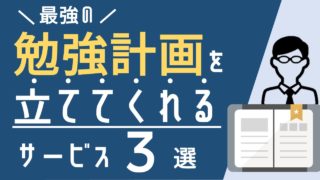

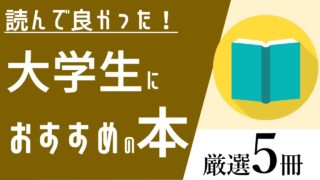
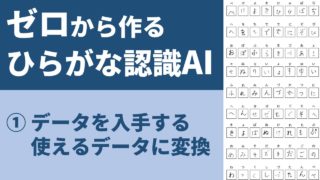
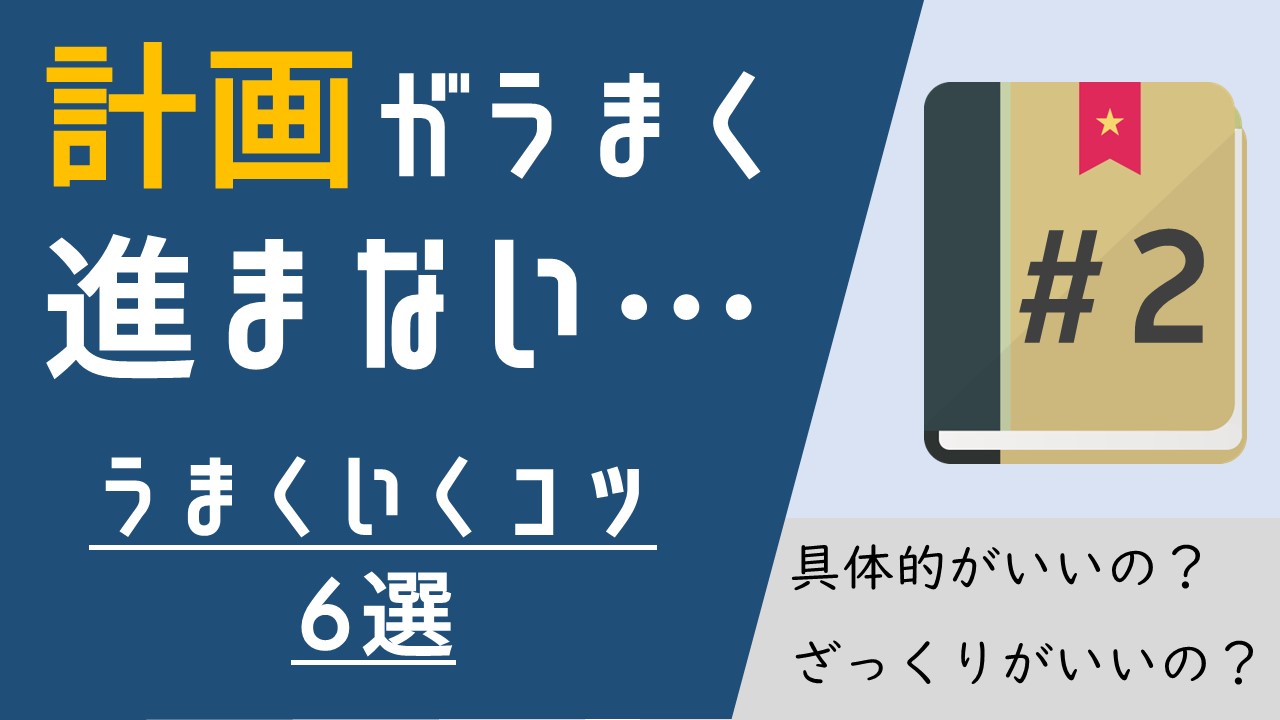


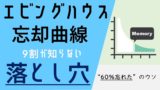

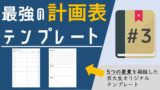

記事への意見・感想はコチラ