
文法・単語は完璧にしたのに、
古文が読めなーい!
こういった悩みを解消していきます。
実際に、受験生からも
文法や単語は暗記しようとするのですが、読解と有機的に結びついていかず行き詰まっています。
という質問が来ました。
古文は基礎知識すら身についていない人(京大志望でも!)が大量にいるので、
そういう意味では、コスパが比較的高い科目です。
この勉強法を実践すれば、簡単に周りと差をつけることができます。
1.身につけた知識を使えるようにするには、長期記憶に移せ
2.問題集の解き方2パターン【具体的に解説する】
身につけた知識を使えるようにするには、長期記憶に移す
古文に限った話ではないのですが、
自分の知識を応用問題に生かすためには、
“無意識的に”知識を取り出せる状態にしなければなりません。
つまり、こういうことです。
ある単語をみて、「えーっと、○○だ!」
という状態は、「うわべだけの知識」です。
一方、知識が長期記憶として蓄えられている状態では、
「○○だ!」と言葉にする前に、反射的に頭に浮かんできます。
この記事を読んでいて、
「この漢字はこうやって読む!」
などと意識しないのと同じです。
なので、単語・文法を読解でも使えるようにするには、
現代語の意味を隠してその意味が言えるだけでは、実は不十分なのです。
そうなるとゴロで覚えるのは、使える知識にする方法としては不向きだといえます。
いちいちゴロを唱えなければ単語の意味が出てこなくなるし、単純暗記になってしまいます。
とはいえ、ゴロは「単純暗記」という面では優れています。
なのでゴロはド忘れした時の“保険”として備えておくもの
という位置づけをしてください。
話を戻しますが、使える知識として頭に入れるためには、
「実際の古文の中で覚える」ということをすればいいです。
下の記事では「英単語」について書きましたが、原理はほとんど一緒です。
単語を見て、反射的にイメージが湧いてくるのが理想。
ゴロ暗記はあくまで保険。
じゃあ結局、問題集はどう取り組めばいいのか
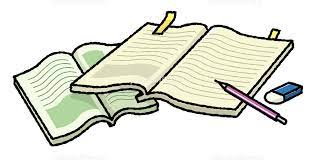
たまに
「単語と文法を完璧に覚えてから読解をやる」
という人がいるのですが、
そのやり方だと効率が悪いし、定着度も下がります。
というのも、「単語・文法を完璧に覚える」という基準がよくわからないし、
いざ古文を読んでみると、全然覚えられてないことに気づくことがほとんどだからです。
効率的な学習法は、
古文を読みながら基礎知識を増やしていくことです。
実際に古文の読解問題を解くときには、次のように取り組むのがいいと思います。
各自のレベルに合わせて実践してください。
【パターン1】
品詞分解をしながら古文を読む
⇒解説をみて、自分の品詞分解と照らし合わせる
⇒間違っていた品詞分解については、そのように分解できる根拠を学ぶ
(例)
自分の品詞分解 /飛び急ぐ/さへ/あはれ/なり/。
正解の品詞分解 /飛び急ぐ/さへ/あはれなり/。
⇒どうして「あはれ/なり」と分けてはいけないのだろうか?
⇒自分は「あはれ」を形容詞・「なり」を断定の助動詞だと捉えたけれど、断定の「なり」は体言(連体形)にしかつかないから、この分解はおかしかったのか。正しくは「あはれなり」でひとつの形容動詞、か。
⇒ん?文法書見たら断定の「なり」だけでなくて伝聞の「なり」もあるぞ!?じゃあ伝聞の「なり」は……
【パターン2】
一応訳せる程度にはなったが、この部分が何を言っているか分からない。
⇒現代語訳は見ずに、品詞分解・逐語訳(不自然な日本語でよい)をする。
この際、“単語帳で”調べてもOK(辞書はNG)。不明な単語は古文のまま処理する。
⇒自分の逐語訳から、精一杯意味を取る。
⇒現代語訳と照らし合わせ、どこが理解できれば意味を解釈できたのかを考える
……主語がわからなかった・逐語訳が不自然すぎた・現代では考えられないことをやっていた など
⇒それぞれ、どのように対策・意識すればいいのか考える
……主語がわからなかった→次はすべての述語に対して、主語を書き込んでみよう
……逐語訳が不自然すぎた→単語帳で、ほかの訳し方も見てみよう
……一人の男性に何人も妻がいるとは思わなかった→古文常識を勉強しよう
(例)
次に、また、曲の物一つ教へ奉り給ふに、いと同じく弾き取り給ふに、尚侍のおとど、さべきにて、おはすると見奉り給ふに、ゆかしくなむとて弾き立て給ひ、掻き合はせ給へるほどに、涙の落ちつつのたまふ。
①品詞分解
次/に、/また、/曲/の/物/一つ/教へ/奉り/給ふ/に、/いと/同じく/弾き取り/給ふ/に、/尚侍/の/おとど/、さ/べき/に/て、/かく/おはする/と/見/奉り/給ふ/に、/ゆかしく/なむ/と/て/弾き立て/給ひ、/掻き合はせ/給へ/る/ほど/に、/涙/の/落ち/つつ/のたまふ。
②逐語訳
次に、また、曲の物を一つ教え申し上げなさると、まったく同じように弾き取りなさると、尚侍のおとどが、そうなるはずであって、このようにいらっしゃると見申し上げなさって、知りたいと弾き立てなさり、搔き合わせなさるときに、涙が落ちながらおっしゃる。
③「訳せたがまったく意味が分からない…。」→ 解説と照らし合わせる
次に、また、(尚侍が“いぬ宮“に)曲を一つ教え申し上げなさると、まったく同じように弾きおぼえなさるので、尚侍は、そうなる(=琴の秘曲を伝授される)はずの人として、このように(生まれてきて)いらっしゃると見申し上げなさって、(どれほど上達するのか)知りたいとしきりに弾きなさって、(いぬ宮と)合奏なさっているうちに、涙が落ちながらおっしゃる。
④理解できなかった原因を分析する
・主語や目的語が省略されているので、イメージをつかめないまま読み進めてしまった。
⇒主語や目的語が省略されているときは、自分で補うことを意識して練習しよう
・「尚寺のおとど≠尚寺」だと思いこんでいた
⇒古文常識、特に敬称・地位に関するものを確認しておこう
など…
自分で書いた品詞分解(+逐語訳)と解答を照らし合わせ、自分に足りない知識を蓄える。
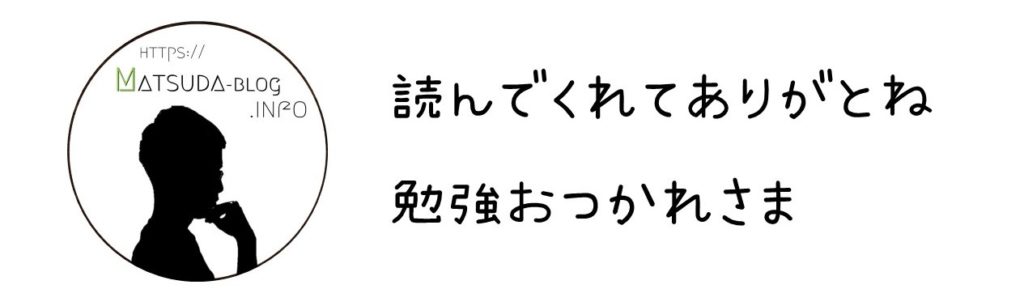

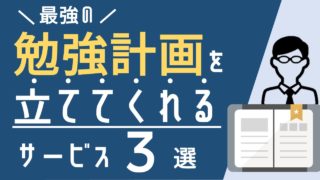

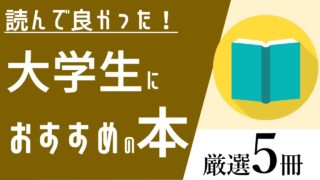
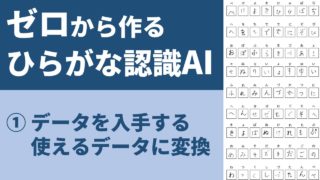
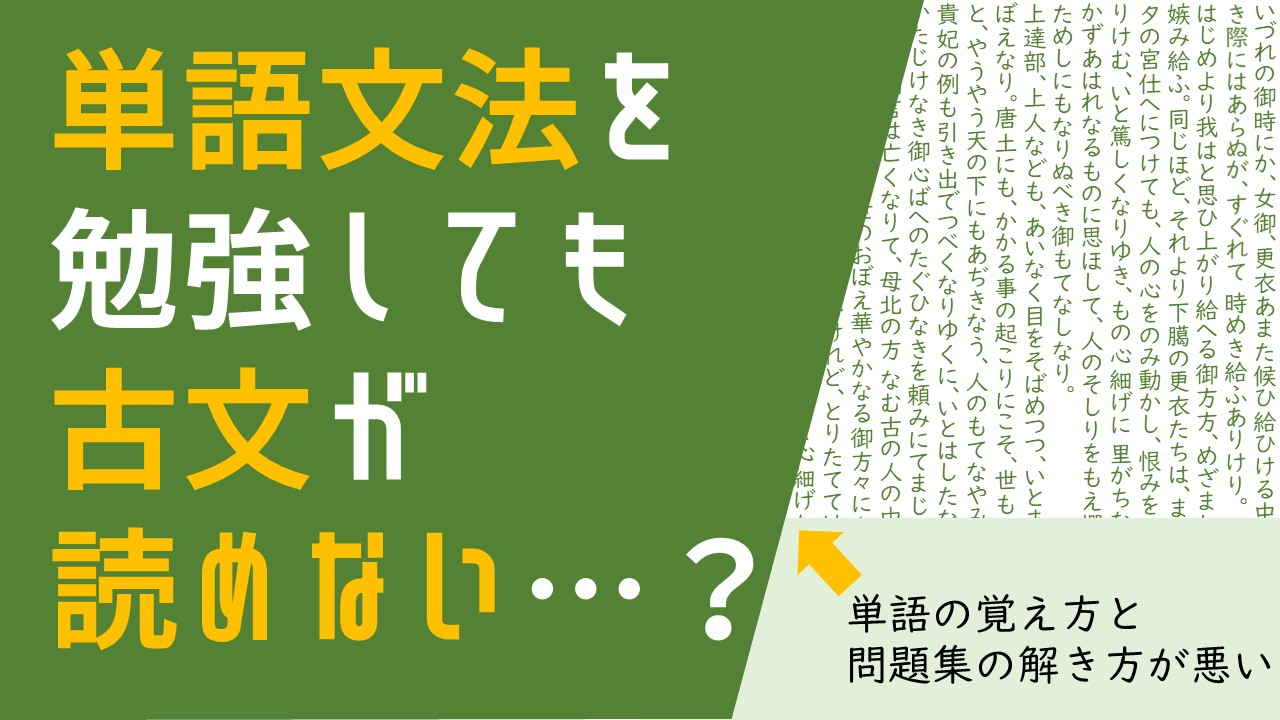

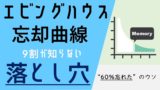





記事への意見・感想はコチラ