
本を読みたいけど、どれを読もうか迷うー!
こういう悩みを持つ大学生のために、5冊にしぼって紹介します!
ここでは僕が最近読んだ、下の表にある5冊の本をおすすめします。
| 書名 | ジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ファクトフルネス | ビジネス書 (社会) | ★★★ | ★★☆ |
| 失敗の科学 | ビジネス書 (経営) | ★★★ | ★★★ |
| 人生は20代で決まる | エッセイ (心理学) | ★★☆ | ★★☆ |
| ヒットの設計図 | ビジネス書 (マーケティング) | ★★☆ | ★☆☆ |
| 統計学は最強の学問である | ビジネス書 (データ分析) | ★★★ | ★★☆ |
ちなみに、表にある「読みやすさ」は
・文章量
・文章の簡潔さ(翻訳本はやや読みにくかったりします…)
などを加味して評価しています。
個人の感想なので、「おもしろ度」「読みやすさ」はあくまで参考程度にして、実際に自分の目で確かめるのが1番です!
ファクトフルネス
| 本のジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ビジネス書(社会) | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
「ファクトフルネス」は、日本で100万部以上を売り上げたベストセラーです。
この本を読むと、僕たち人間が陥ってしまいがちな誤った考え方、いわゆる「バイアス」から抜け出す方法を学ぶことができます。
著者がまとめた”今の世界”についての客観的なデータと、著者自身の体験を交えた内容になっているので非常に説得力がありました。
さっそくページを開いてみると「13個のクイズ」があります。
例えば
・世界の平均寿命は、およそ何歳でしょう?
・世界中の1歳児の中で、予防接種を受けている子どもはどのくらいいるでしょう?
というクイズです。

日本だったら平均寿命80才くらいだけど、世界には医療制度が整っていない国はたくさんいるだろうから…?
と色々考えてクイズに答えるわけですが、僕は見事に引っかかってしまいました。
こういう風に、自分の思い込みで判断してしまうと誤った結論を出してしまう恐れがあります。
僕たちがどれほど”思い込み”に振り回されているかを思い知らされました。
第2章 「世界はどんどん悪くなっているという思い込み」ネガティブ本能
Q:世界の人口のうち、極度の貧困にある人の割合は、過去20年でどう変わったでしょう?
A.約2倍になった
B.あまり変わっていない
C.約半分になった
このクイズに答えてみてください。
僕は「B」を選びました。
しかし…。答えは「C.約半分になった」でした。
著者が行った調査結果によれば、これを正解できた人の割合は、ほとんどの国で10%以下だったそうです。
この結果から、大勢の人が世界を”必要以上に”ネガティブに捉えてしまっている、ということがわかります。
著者は、
暗い話はニュースになりやすいが、明るい話はニュースになりにくい。… [中略] …「小さな進歩」の繰り返しが世界を変え、数々の奇跡を起こしてきた。とはいえ、一つひとつの変化はゆっくりで細切れだから、なかなかニュースには取り上げられない。
p.65-66
と考察しています。
もちろん、極度の貧困にある人がゼロになったわけではないので、もっと努力を続けていかなければならなりません。
しかし「現状を正しく見る目」がなければ、正しい努力はできません。
データをもと世界を正しく見ることが大事なのだ、と本の中で繰り返し主張されています。
失敗の科学
| 本のジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ビジネス書(経営) | ★★★★★ | ★★★★☆ |

「失敗は成功のもと」
と、わかってはいるんだけどね…。
と感じている人は、絶対に読むべき本です。
この本の主なポイントは次の3つ。
「”失敗”したら、それとどう向き合うべきか?」
「人はなぜ、”失敗”を隠したり正当化してしまうのか?」
「”失敗”から学んで、成功するとはどういうことか?」
これらのポイントが、医療ミス・航空事故・経営…といった具体例を通して、徹底的に説明されています。
また、著者は
「”失敗”は、成功のために不可欠だ」
とも述べています。
失敗は「忌むべき悪い存在」ではなく、むしろ「成功に不可欠な存在」だということを学べました。
第1章 失敗のマネジメント
ある人が”失敗”を犯してしまったら、本当にその人を責めるべきなのでしょうか。
確かに、単純な不注意であればその人に責任があると言ってもよいでしょう。
しかし、その人が置かれた環境(システム)が”失敗”をしやすい状況だったら、そうではありません。
著者は、
「個人」ではなく「システム」を見よ
と述べています。
つまり、
もし、Aさんが全力を尽くしたのに失敗を犯してしまったら、Aさんを責めるべきではない。Aさんが失敗したのは、Aさんが置かれた状況のどこが問題だったか?を考えるべきだ。
ということなのです。
人生は20代で決まる
| 本のジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| エッセイ(心理学) | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
心理学者カウンセラーが、「20代」という時期が人生で果たす役割を客観的な視点で教えてくれる本です。
この記事を書いている今の僕は、ちょうど20歳です。
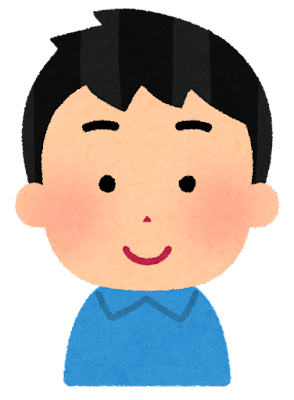
人生、まだまだこれからだし…!
と、なんとなく思っていましたが、この本を読んで

30代になってからじゃ遅い!?
のんびりしている暇はないぞ…。
と考えるようになりました。
著者は20代を中心にしたカウンセラーをしているため、この本の内容が本当に「自分事」として頭に入ってきました。
さらに著者は心理学者で、しかも20代の心理を専門にしている方なので、客観的な事実をもとに話が展開されていて説得力がありました。
これから20代になる人たち・今20代の人たちには、ぜひ一読してもらいたい本です。
11章 結果を予測する
著者はこの章の中で、こう述べています。
20代に達するころ、人間の脳は最終的な大きさになりますが、神経細胞のネットワークは依然として発達中です。
20代は脳の成長にラストスパートがかかる時期です。もちろん、20代以降も脳は柔軟性をもって発達もしますが、20代のときのような大きなチャンスは二度とありません。
p.224,226
つまり、20代を逃してしまうと脳を大きく成長させるチャンスは二度とないぞ、ということです。
こんなことを言われたら、20代をムダに過ごすわけにはいかない!という気持ちになりますよね。
ヒットの設計図
| 本のジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ビジネス書(マーケティング) | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
この本は、
「なぜこの作品がヒットしたのか?」
「流行らないと予想されていたのに、ヒットしたのはなぜ?」
といったヒットの仕組みを考察した本です。
構成としては、まず作品や商品がヒットするまでの詳しいエピソードが語られ、その後「なぜヒットしたか?」を考察するという流れになっていました。
僕たちが何気なく接している、作品・商品・サービスがどのような仕組みでヒットしたのかを、人々の心理に焦点を当てて解説されています。

中身は同じようなアイデアなのに、売れるものと売れないものに分かれてしまうのはなぜ?
といったことも考察されていて、とても面白かったです。
ただ、僕はこの本を読むのに結構な時間がかかりました…。
第1章 人はなじみのあるものを好む
この章では、
人は、「前代未聞の全く新しいもの」よりも「確かに新しいけど、どこか馴染みがあるようなもの」を好む。
といったことが主張されています。
その根拠の1つとして挙げられている、心理学実験を紹介します。
意味のない言葉、でたらめの形、漢字に似た文字などを実験参加者に見せて、どれが好きかを尋ねた。
その結果、実験参加者は一番多くみせられたものを好きだと答えたことがわかった。
p.41-42 (一部改変)
いわゆる「単純接触効果」ってやつです。
無意識のうちに、こうやって情報を脳が処理していると思うと、何か不思議な感じがしますね…。
この章の主張は、本全体を通して貫かれているので、第1章を読むだけでも十分学べると思います。
統計学は最強の学問である
| 本のジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ビジネス書(データ分析) | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
統計学入門レベルの内容を、数式をほとんど使わず、図表を用いながらわかりやすく解説している本です。
「統計学がどうやって使われているか?」ということが具体的にわかるようになっていて、統計学の応用の可能性を実感できました。
しかし統計学は誤った使い方をされやすい学問でもあります。
著者はその部分についてもきちんと解説されていて、統計リテラシーを養うという観点で見ても学びのある本だと思いました。
第4章 「ランダム化」という最強の武器
この章では、さまざまな分野で応用されている科学的手法について解説されています。
その名は「ランダム化比較実験(RCT)」といいます。
この手法はかなり強力で、「ランダム化比較実験」を使った貧困緩和の研究で2019年ノーベル経済学賞を受賞しています。
この「ランダム化比較実験」とは何か?をとても単純に言うと、
被験者をランダムに2つ(以上)のグループに分けてくらべる、という方法
です。
このようにランダムに被験者を分けることで、
「あ…このグループ、お金持ちばかりになってたわ」
「僕らが気付いていない偏りがあるかも…」
という事態を避けることができます。
世の中は複雑で、カオスです。
そのカオスな中でも、実験の条件をコントロールできる(現時点で)唯一の方法がこの「ランダム化比較実験」なのです。
最後に
いかがだったでしょうか。
一言に「本」といっても、膨大な数と種類の本があります。
これだけ多くの本があると、どれを読めばいいか迷ってしまうのも当然です。
しかし、1冊でも本を読むと
「もっと知りたい」
「こんな学問もあるのか、今度はその本を…」
と興味関心を広げることができます。
本は知識の量を増やすだけではなく、興味の幅を広げるものでもあると、僕は思っています。
僕自身も、これからも本を読んで知識と興味を増やしていきたいと思います。一緒に頑張りましょう!
| 書名 | ジャンル | おもしろ度 | 読みやすさ |
| ファクトフルネス | ビジネス書 (社会) | ★★★ | ★★☆ |
| 失敗の科学 | ビジネス書 (経営) | ★★★ | ★★★ |
| 人生は20代で決まる | エッセイ (心理学) | ★★☆ | ★★☆ |
| ヒットの設計図 | ビジネス書 (マーケティング) | ★★☆ | ★☆☆ |
| 統計学は最強の学問である | ビジネス書 (データ分析) | ★★★ | ★★☆ |

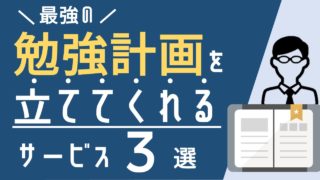

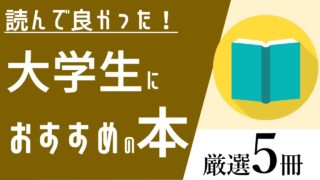
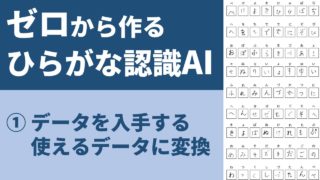
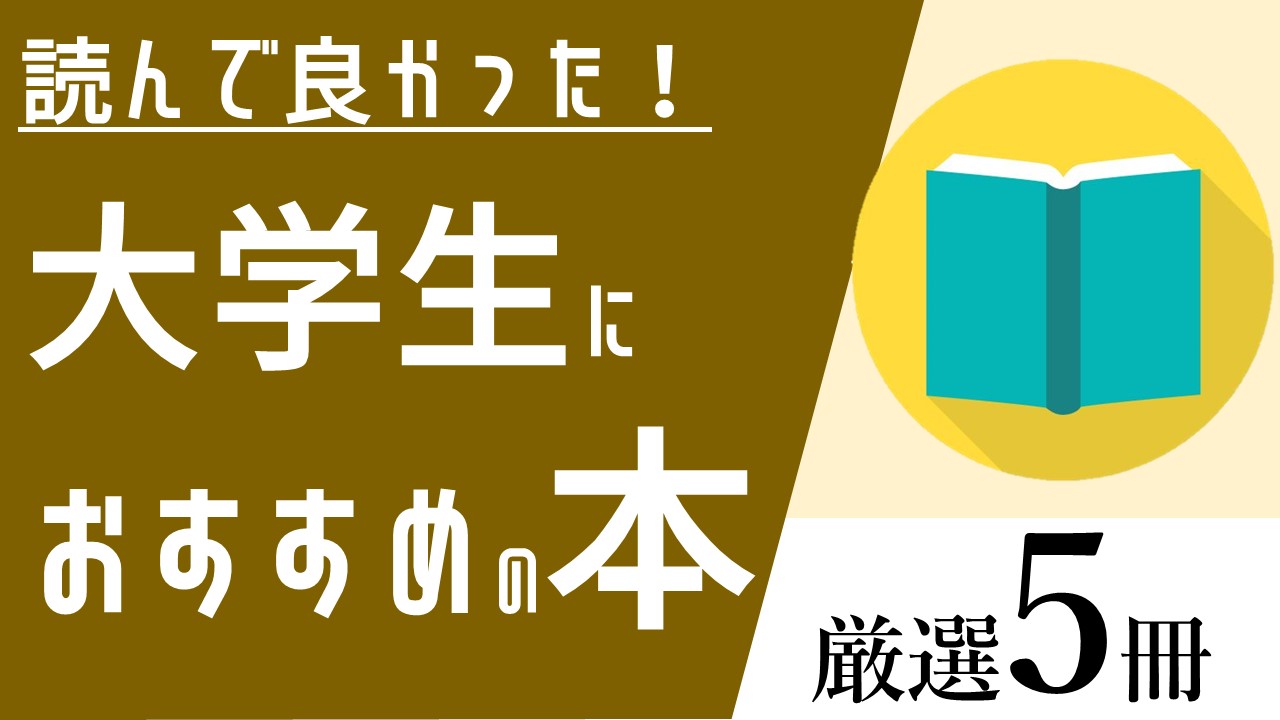
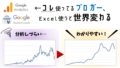
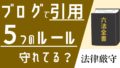
記事への意見・感想はコチラ