
ブログ始めたんだけど、この引用の仕方であってるのかな…?

そもそも許可なしで著作物って利用していいの?
今回はこういった疑問に答えていきます。
本記事では、引用のルールについて解説していきます。
本記事は、こちらの書籍及び複数のWeb記事の情報をもとに執筆しました。
なお、法改正等により事情が変化している場合があります。予めご了承ください。
引用
この5つを守れば、無断引用OK!

著作物を利用するときは、いつも著作権者から許可をもらわないといけないの…?
と思う方がいるかもしれません。
しかし著作権法によって、”一定の場合”には許可なく著作物を利用できるようになっています。
いま言った”一定の場合”には色々な”場合”が含まれますが、そのうちの一つに「引用」があります。
しかし一言に「引用」といっても、どういう場合が引用なのかがわかりませんよね。
どういう場合に「引用」となるのかについては、いろいろ学説や判例がありますが、だいたい次の5つにまとめられます。
- 引用はサブ、メインはあなたの文章 (主従関係)
- 引用部分がはっきりわかる (明瞭区別性)
- 引用元を明示する (出所明示)
- 引用する「必然性」がある
- すでに公表されている著作物から引用する
では、ひとつずつ見ていきます。
引用はサブ、メインがあなたの文章【主従関係】
引用する際は、
「引用がメインなのかサブなのか」
に注意しなければなりません。
まず、ダメな例を見てみましょう。
ベストセラー小説「○○○○」にはこんなシーンがあります↓↓
……
【大量に引用】
……
とても面白いですよね!では今日はこの辺で…。
この場合は、大量に引用しており
メイン:小説の引用
サブ:自分の感想
となってしまっています。
この場合は「引用」には該当せず、アウトです。
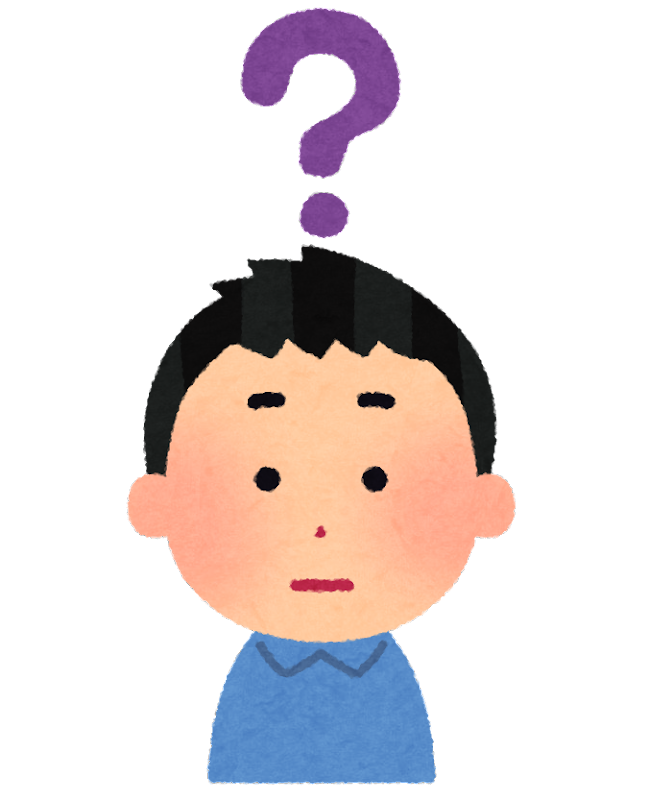
じゃあ、大量に引用しなければ大丈夫なんでしょ?
と思う人もいるかもしれませんが、そうとは限りません。
文章の内容的にも「あくまでメインは自分の文章!」となっていなければならないので注意が必要です。
ベストセラー小説「○○○○」にはこんなシーンがあります↓↓
……
【数行の引用】
……
この表現には著者の独特な特徴が表れている。……【感想・批評がつづく】
一方こちらの場合はセーフです。
ここでは、
メイン:自分の感想・批評
サブ:小説の引用
となっているので「引用」として認められるでしょう。
引用部分がはっきりわかる【明瞭区別性】
引用するときは「この部分が引用です!」とはっきりわかるようにする義務があります。
AはBです。というのも、ある調査を行ったところ○○○○ということが分かったからです。私の考えでは、△△△なので、□□□になると予想することができます。
この例では、自分で考えた文章の中に引用が混じってしまっています。
こうなっていると「どこが引用で、どこがあなたの意見?」ということがわかりません。
しかも、筆者は引用のつもりで書いたのに、読み手からするとあたかも筆者の意見のように見えてしまうこともあるでしょう。
そうなっては著作権者がかわいそうですよね。
それを防ぐために、引用部分は他の部分とはっきり区別できるようにしておく必要があります。
AはBです。実際、次のような調査結果も出ています。
「3000人を対象とした調査により、○○○○ということが判明した。」
(鈴木花子『○○の研究』■■誌 第10号 (2017年) p.101)
私の考えでは、△△△なので、□□□になると予想することができます。
引用元を明示する【出所明示】

引用するときは、出典を書く!
と、皆さんもしっかりと理解していると思います。
しかし、1つ注意点があります。
それは「引用部分に近い所に出典を書く」ということです。
……
「AはBである。」
……
……
……
【出典まとめ】
・山田太郎 『○○論(第3版)』(△△出版,2018年) p.115-116
・……
よくやってしまいがちなのが、引用元を最後にまとめて書いてしまうことです。
できる限り「引用部分」と「引用元」は近接した位置に置かなければなりません。
ただし「引用元が長すぎて、文と文のつながりが分かりにくくなる…」などやむを得ないときは、印をつけておいて、節や記事の最後に引用元の詳細を書くこともできます。
……
「AはBである。」
山田太郎 『○○論(第3版)』(△△出版,2018年) p.115-116
……
【例】Wikipediaから引用するときは…
ウィキペディアから引用する人は結構多いのではないでしょうか。
そこで、ウィキペディアの記事を引用するときの例を紹介します。
*詳細は下のURL(『Wikipediaを利用する』)で確認してください。
Wikipediaの出典の書き方テンプレート
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。
「著作物」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2021年1月28日 (木) 20:02 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/著作物#著作物の定義
①:タイトル
②:『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
(外国語版を使った場合はそれをかく)
③:Wikipedia記事の最終更新日
(Wikipedia記事の最下部に書いてある)
④:Wikipedia記事のURL
引用する「必然性」がある
言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、引用する正当な目的がないとアウトになります。
「ある夜明けのことだった。……【小説からの引用】……」
(鈴木太郎 『○○○○』 p.58)
さて、今回は私が読んだ小説の中でおすすめの10冊を紹介します!
例えばこの例では、
小説の1節からの引用 → 本10冊を紹介
という流れになっています。
しかし、最初の引用は必ずしも必要ではないと考えられます。
この場合、引用する必然性がないとしてアウトになる可能性があります。
「ある夜明けのことだった。……【小説からの引用】……」
(鈴木太郎 『○○○○』 p.58)
この表現、とても風情があって面白くないですか…!
小説を読むことで、このような面白い表現にたくさん出会うことができます。今回はそんな面白い表現が豊富にある小説10冊を紹介します!
一方、この場合はセーフになりそうです。
「小説の引用を用いることで、読者に小説の魅力を伝える」という正当な引用の目的が考えられるからです。
引用をするときは「本当にその引用は必要か?」をきちんと吟味しておきましょう。
すでに公表されている著作物から引用する
著作物なら何でも勝手に引用してよいかというと、そうではありません。
法律で認められる特別の場合を除き「公に出ている著作物」から引用しなければなりません。
研究者である知り合いから、未発表の研究資料を頂きました。その資料によると、
「○○○な人は△△△になる可能性が3倍も高いことがわかる。」
ということらしいです。なので……
例えばこの例では「未発表の研究資料」から引用しています。つまり「公表されていない著作物」を引用しています。
もし、その「研究者である知り合い」から許可を得ていないのであれば、引用することはできません。
まとめ
- 引用はサブ、メインはあなたの文章 (主従関係)
- 引用部分がはっきりわかる (明瞭区別性)
- 引用元を明示する (出所明示)
- 引用する「必然性」がある
- すでに公表されている著作物から引用する
引用の要件をもう一度確認しておきましょう。
太字で示した1,2の要件は特に重要なので、よく注意しながらブログを書きましょうね!

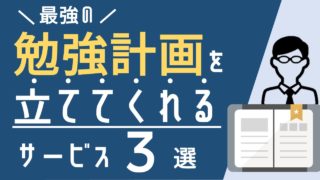

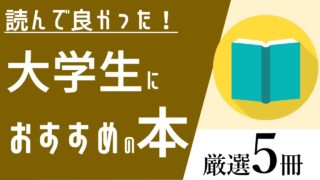
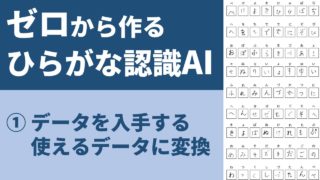
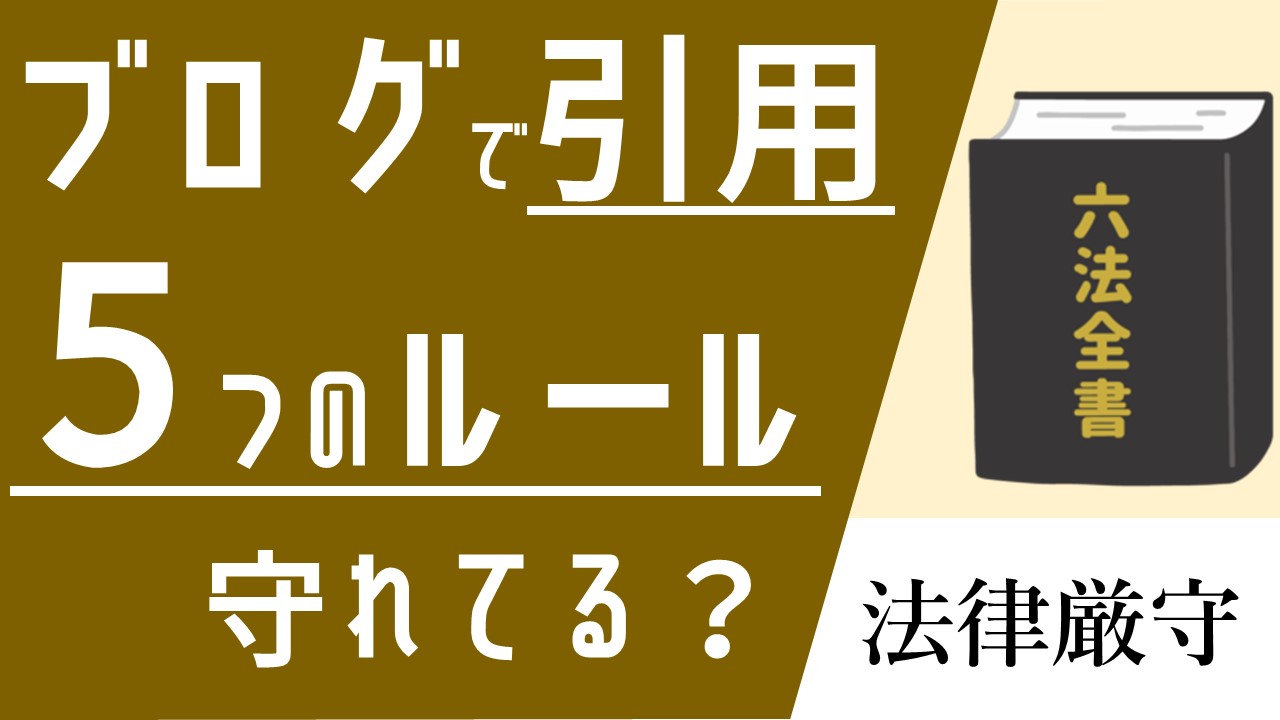


記事への意見・感想はコチラ